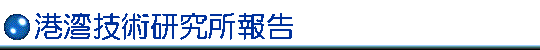
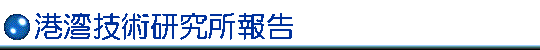
アジア圏域を軸とした21世紀の日本の海運像(CALSによるコンテナ流動ネットワークとアジアが結ぶ世界高速コンテナ航路の形成)
港湾技研報告 VOL.035 NO.01 1996.03
| 執筆者 | 高橋宏直 |
| 所属 | 計画設計基準部 システム研究室 |
要旨 | 近年のコンテナ貨物量の純流動量は著しく増加しており、 世界におけるコンテナ純流動量は93年で3200万TEU となっている。そして、この3200万TEUの内容をみる と、アジア−北米が740万TEU、アジア−欧州が455 万TEU、アジア域内が500万TEUとアジア関連の合計 で1700万TEUに達している。これに北米−欧州の30 5万TEU、欧州域内流動の600万TEUを加えると80 %に達する。このように、世界のコンテナ流動はアジア、北 米、欧州の3極体制となっている。特にアジアにOD(Or igin−Destinaiton:起終点)を有するコン テナ純流動量は全体の50%以上に達していることがわかる 。 しかしながら、アジア圏域のコンテナ流動の構造分析は、 十分になされていなかった。さらに、それを踏まえた今後の 日本のコンテナ動向の検討も十分ではなかった。 したがって、本研究では、アジア圏域を軸としたコンテナ 流動から21世紀の日本の海運像を描き出すことを試みる。 そして、具体的な海運像として、第一に、CALS(Com merce At Light Speed)と結び付けた アジア圏域内のコンテナネットワークの形式、第二に、アジ アが中心となって、北米、欧州とを結ぶ世界高速コンテナ航 路体系の形成という二つの姿を示す。なお、本論文では、ア ジアの中で大半のコンテナが発生・集中する日本からシンガ ポールにかけてのエリアをアジア圏域として表現する。 |
| お問い合わせはkikaku@ysk.nilim.go.jpまでお願いします。 |
| (C)Copyright 1996-2007 Nationnal Institute for Land and Infastructure Management(NILIM) No reproduction or republication without permission. |