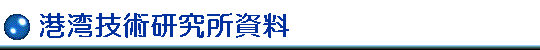
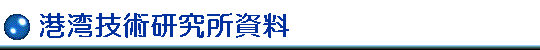
干潟実験施設を用いた物質収支観測
港湾技研資料 NO.0832 1996.06
| 執筆者 | 細川恭史,桑江朝比呂,三好英一,室善一朗,木部英治 |
| 所属 | 海洋環境部 海水浄化研究室 |
要旨 | 当研究所では1994年にメソコスムのサイズスケールを 持つ干潟実験施設を整備した。この施設を利用し、自由に環 境条件を設定した実験から得られる知見は、港湾における干 潟の修復や創生を考える際に大いに役立つと思われる。本研 究では、?この干潟実験施設の概要、?実験施設内水槽の壁 面が底生生物分布に与える影響、?1995年夏期の物質収 支に関する実験についてまとめた。 水槽壁面の底生生物への影響に関しては、実験に用いた生 物の現存量の分布に、壁面が直接影響を及ぼしていないと判 断された。今後、壁面がベントスの代謝速度に及ぼす影響に ついても調査する必要がある。 物質収支に関する実験からは、干潟がいつでも浄化機能を 有しているわけではないことがわかった。6月に比べて7月 はどの物質もsink(干潟に物質が蓄積すること)になる 傾向があった。この理由として、7月の実験における物質の inputが多かったことと、7月から9月にかけて、各水 槽の泥面に珪藻類および藍藻類を主とした底生藻類の大増殖 が起こり、matが形成されたことが推察された。実験水槽 内の生態系は、運転開始から約半年しか時間が経過していな く、遷移の初期段階にあるといえる。この段階の生態系はま だバランスがとれておらず不安定である。底生藻類のmat 形成やコケゴカイの大増殖と急激な衰退は、その典型的な例 であろう。 |
| お問い合わせはkikaku@ysk.nilim.go.jpまでお願いします。 |
| (C)Copyright 1996-2007 Nationnal Institute for Land and Infastructure Management(NILIM) No reproduction or republication without permission. |