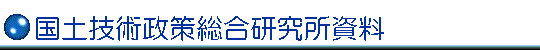
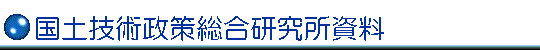
臨海部における空間整備の規範及び評価軸の体系化に関する研究−里浜づくりの理念及び計画手法の確立をめざして−
国総研資料 NO.0097 2003.06
| 執筆者 | 上島顕司,吉村晶子 |
| 所属 | 空港研究部 空港ターミナル研究室 |
要旨 | 平成11年の海岸法改正,平成14年の自然再生法により、臨海部における空間整備 については,今後益々,環境や利用に配慮し,背後地域との一体化を図った空間整備が 要求されることになる。これらの流れを受けて,今まで,等閑視されていた背後地域 と浜の関係性を回復させるような空間整備が要求されているところである。しかし, 背後地域と浜にはそもそもどのような関係性があり,それが今まで海岸整備によって どのような変容を受け,今後,どのように関係性を復活させてゆくべきか,という点は 必ずしも明らかになっていない。また,従来より,利用や景観に配慮した空間整備は 行われてきているが,よかれと思って整備してきてものが必ずしも良い評価を受けな かったり,評価がまちまちであったりして,評価の方法や目指すべき空間の規範が分 かっていないと思われることが多い。このため,本研究では,まず,背後地域と浜が本 来持っていた関係性を明らかにするために,「野」「里山」「鎮守の森」「浜/白砂 青松」の2次的自然と人々の関わり方について民俗学的資料等を分析,比較すること によって,「浜」が本来,持っていた特性を明らかにするとともに,その特性が,従来 の海岸整備により,どのように変容してきたか,今後の臨海部における空間整備のあ り方(理念)はどうあるべきかについて考察した。また、全国各地の臨海部空間の 整備事例の問題点を抽出/分析し,評価軸を体系化することで,恣意的でない評価の あり方及び目指すべき空間の規範,さらに,海岸の空間特性の把握の方法について示 した。 |
| お問い合わせはkikaku@ysk.nilim.go.jpまでお願いします。 |
| (C)Copyright 1996-2007 Nationnal Institute for Land and Infastructure Management(NILIM) No reproduction or republication without permission. |