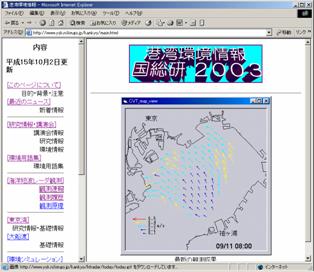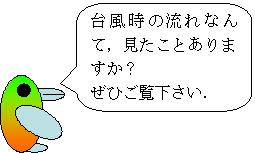海洋短波レーダ(HFレーダ)とは
海洋短波レーダ(HFレーダ)は、短波帯の電波を用いて遠隔地より海面の流れや波を観測するリモートセンシングの機器です.その原理は、Crombie (1955) により発見され、Barrick (1972)らによって実用化されました。
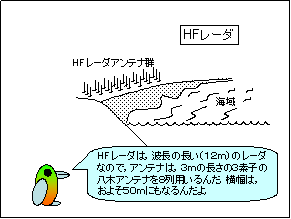
海面の動き(波の移送速度)をドップラーシフトの原理で計測するのですが,電波の周波数や形式,アンテナによるビームのつくり方,信号処理の方式などで世界に10種類程度のHFレーダがあります.
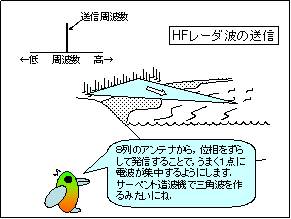
国総研で導入しているレーダは,
・ 位相差素子法のアンテナシステム
・ FM方式のレーダ信号
・ 中心周波数 24.515 MHz
・ 帯域幅 100 kHz
・ ピーク出力100 W(平均50 W)
というスペックで,
・ 最大到達距離 80 km
・ 距離分解能 1.5 km
・ 方向分解能 15°
の計測が可能となっています.
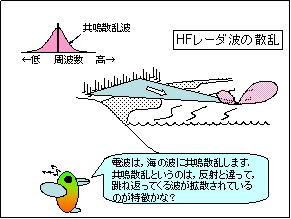
こうしたレーダは,2基1セットで数十km四方の範囲の表面流速を1時間〜数時間毎にモニタリングすることが可能です.
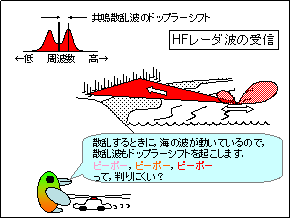
Barrick, D.E. (1972): Remote
sensing of sea state by radar. in Remote Sensing of the Troposphere, Ed. V.E.
Derr, NOAA/Environmental Research Laboratories, pp. 12-1-12-46.
Crombie, D.D. (1955): Doppler
spectrum of sea echo at 13.56 Mc/s, Nature, No. 175, pp. 681-682.
レーダの種類と特性
海洋レーダは、電波の種類、アンテナの形式などで様々な種類があります。
まずは、どのくらいの波長の電波をつかうのかで大きく
・
短波レーダ (High Frequency: HFレーダ) 数MHz〜
・
超短波レーダ (Very High Frequency: VHFレーダ) 30MHz〜
に分かれます。
電波は、周波数が低い方が効率よく伝わり(少ない出力で遠くに届き)ますので、短波レーダの方が、広域の観測に向いています。ただし、分解能は、使える周波数の幅によるので、周波数の幅を広く占有できる超短波レーダの方が一般的に高解像度です。
また、電波の方向を制御する方法として、
・
BF(Beam Forming)
・
DF (Direction Finding) または DBF(Digital Beam Forming)
という2方式があります。前者は、電気的・機械的にアンテナの指向性を作り出し、界面を順次走査する手法で、機構が簡単、データ解析が容易といった特徴を持ちます。後者は、測定範囲全体に照射され散乱してくる信号を同時に受信し、受信信号を処理して方向成分に分けるので、測定時間が短縮できる特徴を持ちます。最近はDBFが多くなってきました。
表−1 世界の海洋短波レーダシステムの例
|
名前 |
周波数 |
帯域幅 |
レンジ |
分解能 |
アンテナ規模 |
変調 |
方向分解 |
|
CRL/NILIM |
24.515 |
100 |
96 |
1.5 |
40 |
FMCW |
BF |
|
CODAR PISCES OSCR COSRAD |
25 7 55 30 |
125 20 600 |
60 200 15 >20 |
1.2 7.5 0.25 3 |
90 200 83 40 |
Pulse FMICW Pulse Pulse |
DF BF BF BF |
|
|
(MHz) |
(kHz) |
(km) |
(km) |
(m) |
|
|
CRL/NILIM (日本):郵政省通信総合研究所の開発による海洋短波レーダ、
CODAR、UH-CODAR (アメリカ):NOAA開発のCODARシステム
PISCES (フランス):トロン大学のシステム
OSCR (イギリス):Marconi開発のOSCRシステム,バーミンガム大学開発のシステム
COSRAD (オーストラリア):ジェームスクック大学のCOSRADシステム
FMICW:周波数変調 BF: Beam Forming, DF: Direction Finding
どんなデータが取れるのか
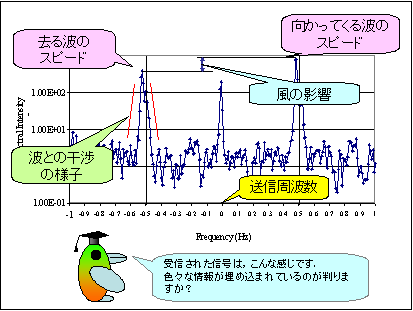
HFレーダでは,表面の流れの他に,波高や波向き,風なども測れると言われていますが,今のところ,実用化されているのは流れの観測だけです.
相模湾で観測した例を下に示します.千葉県の布良と神奈川県の平塚にレーダを設置して,蛇行した黒潮の分枝流が,大島の西側から相模湾を通り,東京湾に到達する様子が捉えられています.また,大島の背後や相模湾沿岸部に渦ができていることも,はっきりと判ります.このデータの明快さがHFレーダの身上です.
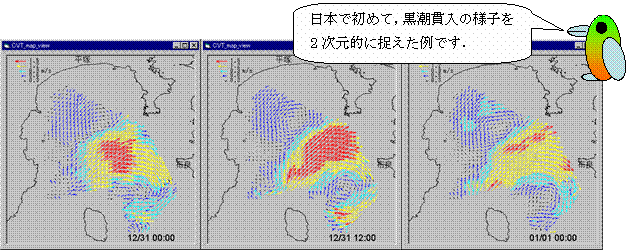
相模湾における計測事例 (2000年12月31日から2001年1月1日にかけての流れ.国総研所有のHFレーダによる観測)
そのデータの利用法について
流れを常時観測できると,様々な利用法が考えられます.
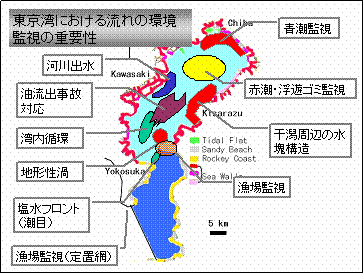 現象の解明だけでなく,湾内の浮遊ゴミの監視,青潮・赤潮の移動の監視,油流出事故への対応,漁業者への情報提供といった利用が考えられます.
現象の解明だけでなく,湾内の浮遊ゴミの監視,青潮・赤潮の移動の監視,油流出事故への対応,漁業者への情報提供といった利用が考えられます.
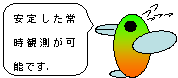
監視体制をさらに充実させるためには,HFレーダによる観測だけでなく,係留モニタリングや環境整備船による観測との連携が効果的です.
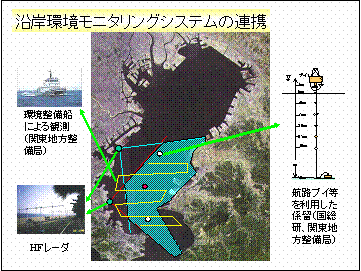
沿岸環境モニタリングで得られるデータは,リアルタイムに東京湾環境情報センターへ送られ,常に新たな情報が利用者に提供されます.
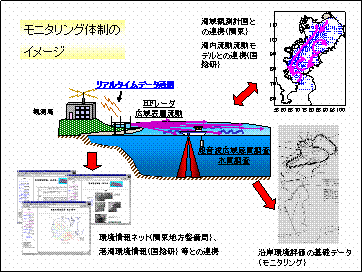
こうしたデータの蓄積は,モデルとの連携で,より詳細な検討を行うことができると共に,港湾計画の検討や事業実施時の参考にすることができます.
HFレーダをめぐる状況
現在,日本には,国総研の他に,海上保安庁・通信総合研究所・北大・九大・三重県が所有するHFレーダがあります.
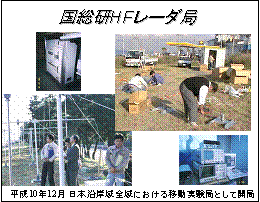
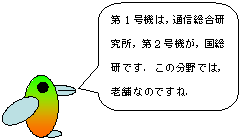
HFレーダは,非常に多くの周波数を占有するために,無尽蔵に免許を受けることができません.内湾域や沿岸域での使用に適した周波数である24MHz帯では,中心周波数 24.515 MHz,帯域幅 100 kHzという領域が唯一HFレーダに許可された領域です.
現在は,先駆的な実験を行った機関(国総研を含む)間の話し合いで,同一周波数を用いた運用が行われています.
興味を持っていただいたら
http://www.nilim.go.jp/
データベース → 環境情報〜東京湾〜 → 海洋短波レーダ観測
をご覧下さい.
http://www.ysk.nilim.go.jp/kankyo/ hfradar/archive/rireki.html
から直接データをご覧になれます.