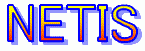
| 入力システムダウンロード | 新技術の入力説明 |
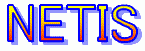
|
|
新技術情報入力システムをインストールする際は、管理者権限のあるユーザでログインしてからインストールを行なって下さい。新技術情報をデータベースに登録するためには、「新技術情報」と「活用の効果の根拠」のデータが必要となります。
ここでは、「新技術情報入力システム」の使い方を説明します。
新技術情報の入力は以下の手順で行って下さい。
新技術情報入力システムの起動方法
“スタート”メニューから、以下の手順で“新技術情報入力システム”を選択すると新技術情報入力システムが起動します。
“スタート”→“プログラム”→“新技術情報入力システム Ver7”→“新技術情報入力システム”
![]()
データ入力の仕方
登録データのリスト表示画面
登録データのリスト表示画面には、入力されたデータの一覧が表示されます。
データが1件もないときには以下のように表示されます。
この画面では
・登録データの「新規登録」、「編集」、「削除」
・入力されたデータから「提出用ファイル作成」
・入力されたデータの「データ取り込み」
を行います。
入力画面
入力項目は文字を入力するもの、リストから選択するもの、チェックマークを付けるものなどがあります。
また、太字で表示されている部分は入力必須項目です。入力項目の中には、半角でしか入力できないものや、空白文字を2個以上続けて入力できないものがあります。
画面に示した入力例に従って入力してください。
◎名称・分類等
<新技術名称>
以下の項目に情報を入力して下さい。特に、太字になっているものに関しては、必ず入力をして下さい。
入力されない場合には登録用ファイルが作成されません。
また、分類は、土木工事共通仕様書、新土木工事積算体系に準拠した工事工種体系の分類となっています。
レベル1から順に選択して下さい。
入力は、漢字・ひらがな等は全角で、英数字は半角でお願いします。
◎概要
<概要等の入力>
概要の欄には、必ず何か情報を入力して下さい。
入力されない場合は、登録用ファイルが作成できません。
情報の入力は、漢字・ひらがな等は全角で、英数字は半角で入力して下さい。
半角カタカナは入力できません。また、空白文字を2個以上続けて入力することもできません。入力できる文字数は、すべて全角で入力した場合は1000文字まで、すべて半角で入力した場合は2000文字までです。
<画像ファイルの選択>
写真あるいは図面等の画像ファイルを指定するには、「選択」ボタンを押してください。
「選択」ボタンを押すとファイル選択のためのダイアログが表示されますので、GIF形式あるいはJPEG形式の画像ファイルを選択してください。
画像ファイルを作成する際の注意事項については、<画像ファイルの作成について>をご覧ください。
「画像ファイルの選択」のウィンドウ
![]()
<画像ファイルの作成について>
新技術情報に関連する写真や図面等は、 WEB(インターネット・イントラネットのシステム)上で表示します。
そのため、まず写真や図面等をスキャナ等でデジタル・データに変換して、画像ファイルとして保存する必要があります。
また、この画像ファイルにはWEB上で表示するためのいくつかの制限がつきます。
以下の注意事項について、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
- 写真や図面等は、スキャナ等でデジタル・データに変換して、画像ファイルとして保存して下さい。
- WEB上に表示できる画像ファイルの形式はGIF形式あるいはJPEG形式です。
- 画像ファイルのサイズは185キロバイト以内のものしか登録できません。
- 画像ファイルはWEBのホームページ上に表示されることになるので、なるべく画面内におさまる大きさで作成して下さい。 特に、横幅が大きくならないように注意し、300ピクセル(ドット)前後の大きさを目安としてください。 それを上回る大きさの画像を表示させたい場合には、最大で横幅が600ピクセル(ドット)を超えないように画像ファイルを作成してください。
- 画像ファイルは以下の箇所にそれぞれ1つずつ登録できます。
- 概要
- 特徴
- 施工方法
- 実験等実施状況
ただし、上記以外の箇所について画像ファイルを登録したい場合には、<写真>(様式4)の欄に最大で3つまで画像ファイルを追加登録できます。
〜画像ファイル作成手順の一例〜
![]()
◎従来技術との比較
<活用の効果>
活用の効果は、従来の技術に対する新技術の効果を入力する画面です。
比較の対象となる「従来技術名」を全角文字で入力して下さい(なるべく同社保有の従来技術名として下さい)。
半角カタカナは入力できません。また、空白文字を2個以上続けて入力することもできません。各項目に対する新技術の効果を3段階で評価して下さい。
経済性及び工程で同程度以外を選択する場合は、「活用の効果の根拠」にて、新技術及び従来技術の内訳を入力して下さい。
変化値については、「活用の効果の根拠」を入力することにより、自動で数値が表示されます。「比較のポイント」、及び、「その他」は全角文字で入力を行って下さい。
半角カタカナは入力できません。また、空白文字を2個以上続けて入力することもできません。
<活用の効果の根拠>
・一 般
「基準とする数量」及び「単位」を入力して下さい。
新技術と従来技術の「工程」の日数を入力して下さい。
・新技術の内訳
「新技術の内訳」を入力するには、まず、「項目追加」ボタンを押して、入力ダイアログを表示させて下さい。
すでに入力されているデータを編集したい場合は、該当する行を選択してから、「項目編集」ボタンを押して下さい。
すでに入力されているデータを削除したい場合は、該当する行を選択してから、「項目削除」ボタンを押して下さい。
入力・編集のダイアログ
・従来技術の内訳
「新技術の内訳」を入力するには、まず、「項目追加」ボタンを押して、入力ダイアログを表示させて下さい。
すでに入力されているデータを編集したい場合は、該当する行を選択してから、「項目編集」ボタンを押して下さい。
すでに入力されているデータを削除したい場合は、該当する行を選択してから、「項目削除」ボタンを押して下さい。
入力・編集のダイアログ
<表の入力>
表の入力では下の図のように見出しの列と行を指定することができます。
指定した見出しは色で区別されます。
◎施工実績等
<施工実績>
施工実績には、国土交通省及び前運輸省の「実績件数」、「実績」と国土交通省以外の「実績件数」、「実績」があります。
まず、「実績件数」に施工実績の件数を入力します。
件数は、“国土交通省及び前運輸省における実績件数”と“国土交通省以外における実績件数”に分けて入力して下さい。
次に、それぞれの工事件名等も同様に分けて入力して下さい。
「実績」を入力するには、まず、「実績追加」ボタンを押して、入力ダイアログを表示させて下さい。
すでに入力されているデータを編集したい場合は、該当する行を選択してから、「実績編集」ボタンを押して下さい。
すでに入力されているデータを削除したい場合は、該当する行を選択してから、「実績削除」ボタンを押して下さい。
入力・編集のダイアログ
入力・編集のダイアログ
<第三者評価・表彰等と結果>
「第三者評価・表彰等と結果」を入力するには、まず、「追加」ボタンを押して、入力ダイアログを表示させて下さい。
すでに入力されているデータを編集したい場合は、該当する行を選択してから、「編集」ボタンを押して下さい。
すでに入力されているデータを削除したい場合は、該当する行を選択してから、「削除」ボタンを押して下さい。
入力・編集のダイアログ
◎印刷プレビュー
<印刷プレビュー>
「印刷プレビュー」のページでは、入力したデータを印刷することができます。
画面には印刷イメージが表示されます。「印刷プレビュー」の各タブを選択すると選択したタブ項目の内容のみを印刷する
ことができ、「一括印刷」を選択すると全項目の内容を印刷することができます。
「印刷」ボタンを押すと印刷が始まります。
データの保存方法
入力画面で、「保存」ボタンが押せる状態のとき(文字が青いとき)にボタンを押すか、「メニュー」に戻るときにレコードを保存するかどうかを確認します。
「はい」を選択すると編集したデータが保存されます。
![]()
提出用ファイル作成
「メニュー画面」で「提出用ファイル作成」ボタンを押すと、出力先を指定するダイアログが表示されます。
ファイル名には新技術名称が表示され、新技術名称.lzhで保存されます。
![]()
提出用ディスクには、原則として以下のものを使用して下さい。
- 形 状 : 3.5インチディスク
- 種 類 : 2HD(1.44 MB)
- フォーマット: DOS/Vマシンで読込みが可能なもの。
データ取り込み
「メニュー画面」で「データ取り込み」ボタンを押すと、入力元を指定するダイアログが表示されます。
ファイルは新技術名称.lzhを選択して下さい。
以前のバージョン(6.xxx)の新技術を取り込む場合は、ファイルの種類で「旧新技術データ」を選択し、ファイル名はNewTech.nt6を選択して下さい。
![]()
終了方法
「メニュー画面」で「閉じる」ボタンを押すと、プログラムは終了します。
フロッピーディスクの提出について
新技術情報の提出用フロッピーディスクは、以下の提出先まで郵送して下さい。
【東北地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾空港整備・補償課 住 所 : 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア9・10F Tel : 022-716-0007 URL : http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kakyoin/
名 称 : 仙台港湾空港技術調査事務所 技術開発課 住 所 : 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-35 ロイメント仙台7F Tel : 022-791-2113 URL : http://www.pa.thr.mlit.go.jp/sendaigicho/
【関東地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾整備・補償課 住 所 : 〒231-8436 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 Tel : 045-211-7419 URL : http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/
名 称 : 横浜港湾空港技術調査事務所 調査課 住 所 : 〒221-0053 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-4 Tel : 045-461-3895 URL : http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/yokohamagicho/
【北陸地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾空港整備・補償課 住 所 : 〒951-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎一号館 Tel : 025-280-8763 URL : http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/
名 称 : 新潟港湾空港技術調査事務所 技術開発課 住 所 : 〒951-8011 新潟県新潟市中央区入船町4-3778 Tel : 025-224-5080 URL : http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/gicho/
【中部地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾空港整備・補償課 住 所 : 〒455-8545 愛知県名古屋市港区築地町2 Tel : 052-651-6489 URL : http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/
名 称 : 名古屋港湾空港技術調査事務所 技術開発課 住 所 : 〒457-0833 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町1-57-3 Tel : 052-612-9984 URL : http://www.meigi.pa.cbr.mlit.go.jp/
【近畿地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾空港整備・補償課 住 所 : 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎 Tel : 078-391-7322 URL : http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/
名 称 : 神戸港湾空港技術調査事務所 調査課 住 所 : 〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町7-30 Tel : 078-331-0409 URL : http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobegicyo/
【中国地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾空港整備・補償課 住 所 : 〒730-0004 広島県広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白鳥ビル13F Tel : 082-511-3907 URL : http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kouwan/
名 称 : 広島港湾空港技術調査事務所 技術開発課 住 所 : 〒730-0029 広島県広島市中区三川町2-10 愛媛ビル広島6F Tel : 082-545-7018 URL : http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/gicyo/
【四国地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾空港整備・補償課 住 所 : 〒760-8554 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎8F Tel : 087-811-8332 URL : http://www.pa.skr.mlit.go.jp/
名 称 : 高松港湾空港技術調査事務所 技術開発課 住 所 : 〒760-0017 香川県高松市番町1-6-1 住友生命高松ビル2F Tel : 087-811-5661 URL : http://www.pa.skr.mlit.go.jp/tkgityou/
【九州地方整備局】
名 称 : 港湾空港部 港湾整備・補償課 住 所 : 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎 Tel : 092-418-3372 URL : http://www.i-port.go.jp/
名 称 : 下関港湾空港技術調査事務所 技術開発課 住 所 : 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目6-1 下関地方合同庁舎2階 Tel : 083-224-4130 URL : http://www.pa.qsr.mlit.go.jp/gityou/
【北海道開発局】
名 称 : 事業振興部 防災・技術センター技術課 住 所 : 〒060-8511 北海道札幌市豊平区月寒東2条8丁目3―1 Tel : 011-851-4111 URL : http://www.hkd.mlit.go.jp/